潮湯を作った男-大阪の風雲児森口留吉
築港大潮湯の仕掛け人は、森口留吉という人物。築港大潮湯も森口の個人経営でした。
森口は明治8年(1875)12月、河内国志紀郡田井中村(現在の八尾市)に生まれました。
生家は非常に貧乏だったらしく、あまりに貧乏だったが故に、留吉の父が縁起をかつぎ姓を森口に変えたほどでした。しかし貧乏は改まらず、留吉は十三歳で大工修行に入りました。
森口は、豊臣秀吉を理想の人物としていたようで、

太閤さんのようにデカいことやらなあかん!
というのが口癖でした。彼の伝記を書いた松本栄太郎は、彼を「炎の人」と形容した天性の事業家でした。
その言葉どおり、大工の枠をはみ出して土木建築業や銭湯経営にも乗り出していましたが、関西に興った「スーパー銭湯」ブームに、一世一代の「デカいこと」に乗り出しました。それが築港大潮湯でした。
建築工事の際に出る木くずや廃材がもったいない、これを再利用する手はないだろうか…彼はそれを浴場の湯沸かしに使用します。今も昔も燃料費が銭湯経営をかなり圧迫するほどの出費です。が、こちらは自分の事業で起こした廃材だから、燃料費はほぼ自給自足のタダのようなもの。自分の事業コンボで倍々ゲーム。こりゃ森口さん、ええ商売してまっせ。
そんな森口の商売と潮湯の繁盛っぷりを指でくわえて見ていた、ある若者がいました。
彼も産業界に進出したばかりの新進気鋭の青年実業家でしたが、今をときめく起業家の先輩である森口から商売の秘訣を学びたいと自宅に招待。森口も快諾しました。
彼らが具体的に何を話したのか、それは伝わっていません。ビジョンの違いから気は合わなかったとする人もいます。が、森口の垢は少し煎じて飲んだと思われる青年実業家は、「大衆の生活レベル向上」をモットーにし、現代につながる大会社を築き上げました。彼の名は…

松下幸之助。
写真は1929年の頃のものですが、森口に頭を下げた若き時も、こんな姿だったのだと思われます。
関東大震災と築港大潮湯、そして留吉

大正12年(1923)9月1日、東京で関東大震災が起こりました。関東の地震だから大阪は関係な…とお思いでしょうが、実は地震計で震度4を記録しています。
といっても、人的・物的被害はほとんどなかったので、関西、特に大阪が被災者の受け入れ口となりました。文豪谷崎潤一郎が、震災を機に関東から関西へ移住したことは有名です。
そんな中、関一大阪市長(当時)が森口のもとを訪れます。
関は開口一番、結論から切り出しました。
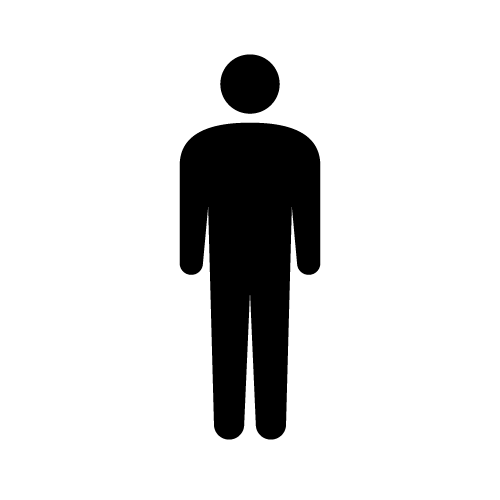
潮湯を被災者収容所として開放してくれないか
人情あふれる森口は、よっしゃ!と一発快諾。それも貸し出し期限は「お気の済むまで」、つまり状況が落ち着くまで。百畳から三八〇畳に拡大されていた大広間を含めた新館は、関東から運ばれてきた被災者の収容所となりました。
.jpg)
.jpg)
(いずれも『炎の人森口留吉・増太郎伝』より)
森口のすごいところは、建物を二つ返事で市に貸しただけではありません。収容者の賄いもすべて引き受け、森口本人もその手伝いをしたそうです。
この大盤振る舞いに、後日、関市長が自ら収容所と化した新館を訪れ、心からの感謝を伝えています。
震災の混乱も落ち着いた大正15年(1926)、留吉は一世一代の大バクチを行います。
なんと、築港大潮湯を売却してしまったのです!
既に前年には新館の一部を、貸事務所として大阪市に寄付してしまったのですが、留吉には何かが見えたのか、まるで捨てるように、潮湯の事業も神戸の汽船会社に売ってしまいました。
そして、それが何と…結果的に吉となることに。それは後述します。



















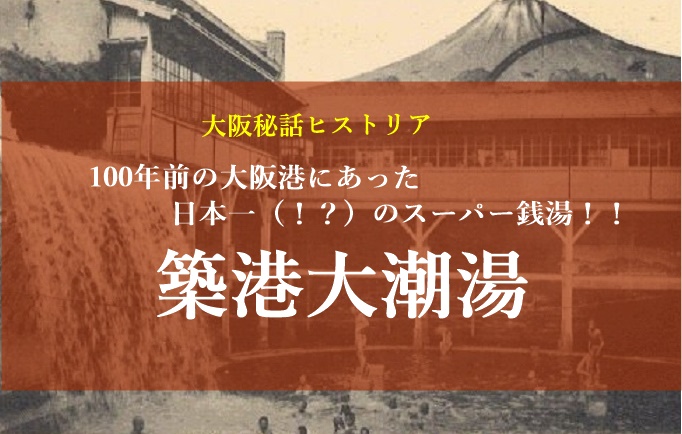

コメント