
焼津とくれば、真っ先に思いつくのが遠洋漁業の街というイメージ。焼津という漢字を見ると「焼」という文字の存在感がなくなってしまうほど、潮の香りを感じる街であります。実際、焼津市のイメージソング名は「今、潮騒のまちへ…」であり、やはり海辺の漁業の町というイメージを前面に出しています。

マグロとカツオの漁獲高は日本一であり、ここに住むと毎日マグロが食えそうな魚好きにとってはこの世の極楽。魚介類大好きな私も、老後は魚市場がある海辺の街に移住して毎日魚を食って死にたいなと思うことがあります。
で、こんなところに遊郭・赤線があるのか?
と考えてしまいますが、以前石巻編でも述べたとおり、「こんなところ」だからこそあるのです。「こんなところ」とは漁業の町ということ。漁師を多く抱える漁港だからこその事情が、遊郭・赤線がある伏線となっていたりします。
今回は、漁業の街にあった赤線のお話。
焼津の赤線ー漁業と切り離せない「女」
焼津の遊里史を調べるために、手始めに戦前の遊郭を調べてみるかと『全国遊廓案内』を開いてみました。すると…

あれ?ない?
焼津に遊郭がない…これは予想外でした。山形県天童のように『全国遊廓案内』に記載されていない遊郭も実際にあるので、載っていないだけと思っていました。が、静岡県の遊郭・赤線を調べた書物にも、
「いかがわしい飲み屋などは何軒かあったが遊廓はなかった」
『静岡県の赤線を歩く』(八木富美夫氏著)
と記載されているので、やはりなかったのでしょう。
しかし、あったのです。
焼津の赤線は、地元の資料によると「特殊飲食店」。要は飲み屋や小料理屋の形態で営業していたと推定されます。赤線現役時の焼津市商工名鑑には、「海望荘、麗月、ハルナ、広月、三楽」など11件の特殊飲食店の名前がズラリ。
地元の古老の話によると、船が漁から帰ってきた日となると、漁師たちが目を血走らせ札束を握りしめながら、

お、女…
と駆け寄ってきたそうです。
いったん出港すると、途中で海外の港に寄港することもあるものの、基本は1~2ケ月くらい海の上となります。
我々にはわからない感覚ですが、何か月も海の上にいると土と共に「女」が非常に恋しくなり、気が狂いそうなくらいに欲するそうです。「オナ禁」というものがありますが、あれをやってみるとわかります、特に若い時は定期的に出さないと精神的にも参るものだと。
それは漁師だけではなく、大日本帝国海軍も同じ。海上で数ケ月も続く演習の帰り、寄港地の陸地が見えると、

「三本足」で立ってたよwww
と述べていた海軍中佐がおりました。
それだけに、陸が見えると乗員の鼻息が荒くなる。そこでさっさと寄港させ部下を陸に揚げ、遊郭やカフェーで女と遊ばせる…これも艦長の腕次第。上陸よしの態勢になったのに上官の顔色を見て上陸を遅らせたり、操艦がへたくそでさっさと所定の位置に着艦できない艦長がいると、士気が著しく下がりました。

(先の戦争中は)そんな艦から沈んでいったわい
第二次大戦中、伝説の不沈艦として「神」と呼ばれた駆逐艦『雪風』を「神」たらしめた名艦長、寺内正道中佐の言葉です。
で、その話を元船員の知人に話したところ…
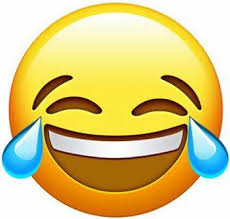
あーそれめっちゃわかるwww
爆笑して同意していました。わかるんかい!
閑話休題。
地元の水産史にも特飲街こと赤線地帯の記述があります。
やはり海の男と女の肌は切っても切れない関係なのでしょう。
焼津にあった二つの赤線
焼津の特飲店がけばいネオンを掲げて営業するようになったのは、昭和26年(1951)頃と資料にあります。
そもそも「小石川」という川沿いの両岸に店が集まり始め、自然と歓楽街を形成するようになりました。
小石川は焼津港へ直接つながるので、港でもある河口あたりに店が集まり始めたのでしょう。
翌27年(1952)になるとすでに30軒近くになっていましたが、ここまで増えると風紀上良くないという意見が出始めるのがいつもの流れです。
これは港や海の男の施設のうちだから必要悪だという意見もあったものの、非漁業従事者からの圧も非常に強く、警察の判断でのちに「弁天地区」と呼ばれるエリアに集約と決まりました。
が!
移転に反対する業者の声も強く、昭和28年(1953)には「移転派」と「残留派」で赤線が二つに分裂してしまいました。
当時の新聞によると、弁天地区に移転した業者は14軒(女55人)、小石川に残った業者は13軒(女60人)で、数字的にはほぼ真っ二つ。
前者は「歓遊池」、後者は「港陽園」と名乗り、それぞれ組合を作って別々に営業を始めました。
が、地の利が良い「港陽園」が繁盛するのは当たり前で、弁天移転組は不満を持ち始めます。
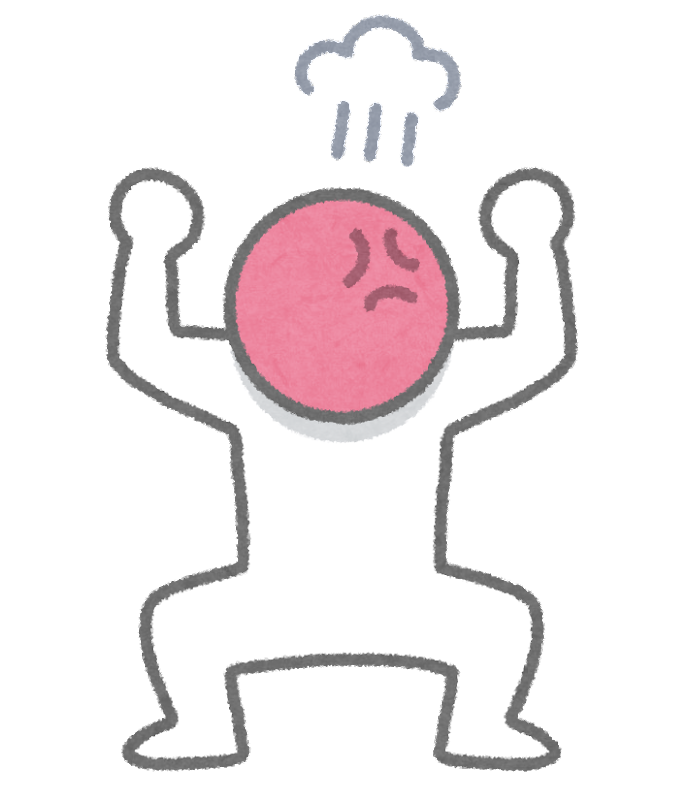
お上の言うことを聞いて移転したのに不公平だ!
行政指導に素直に従った方を見殺しにするのか!とこっちはこっちで圧をかけ始めます。
これは法的には歓遊池側の方に利があり、警察も取り締まりを強化。結局「港陽園」側も弁天地区に移転することになり、小石川の特飲街は昭和29年(1954)には消滅しました。たった3年しか存続しなかった、焼津の幻の赤線ですな。

なぜ焼津の赤線は「弁天地区」と呼ばれていたのか。
そこに鎮座する弁天さん(宗像神社)から「弁天」と呼ばれていたそうです。焼津に来る海の男たちにとって、「焼津の弁天」は女の香りがする特別な場所だったことでしょう。
関西では、遊郭の遊女や現在の風俗のおねーさんを雅に「姫」ということがあります。国語辞典にも江戸時代から上方では遊女のことをそう呼んでいたとあり、江戸でいう「女郎」に相当します。私もそう呼ぶことがありますが、まさか関西独特の表現(ある意味関西弁)だったとは。
それはさておき、弁天様は女性、もしかしてここで働く娼婦たちも海の男たちから隠語で「弁天様」と呼ばれていたかもしれませんね。
そこで働く女も150名以上おり海の男たちで連日にぎわったという焼津の赤線は、昭和33年4月の売防法完全施行につきなくなったのは、他の赤線と同じです。
赤線廃止後の焼津は…
が、海の男のフラストレーションを解消させるのは「臭いものには蓋をしろ」では解決しません。

これ、闇に潜っただけやろな…
何の証拠もないですが、そう予測しました。そして、その予測は当たっていたようです。
売春防止法が日本法制史上とんでもないレベルのザル法だったというのは、いくつかのブログで述べていますが、その穴をくぐり抜け赤線廃止跡もしたたかに営業していた様子が、梶山季之の書物に描かれています。
その中に焼津のその後も含まれていました。23軒あった店は売防法完全施行で14軒が旅館に、2軒がカフェーに、残り7軒は「様子見」とのこと。旅館に転業した元業者も客数が激減して青息吐息の様子でした。最初は漁師などが
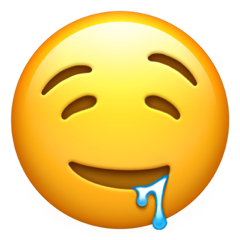
と、泊めさせてくれ…
血走った目をして飛び込んできたものの、女の子はもういませんと対応すると、元々気性が荒い海の男のこと、人によってはケンカになっていました。
しかし、そんな彼らも次第に元赤線に寄りつかなくなりました。漁師たちも観念して「我慢」した?いえ、人間の三大原始欲は売春窟廃止ごときでなくなるわけがありません。
いつのときからか、赤線がなくなった後なことは確かですが、港付近に「屋台」が出没、その数は多いときには4〜50軒ほどありました。
夜ともなると道はギッシリと屋台で埋まるのですが、この屋台、他のと比べてどこかおかしい。その屋台には、少なくても3名、多いところでは7〜8名の女がいるのです。
ある漁師が屋台でお酒を飲んで店の女の子とおしゃべりをしていました。明らかに男が女を口説いている様子。
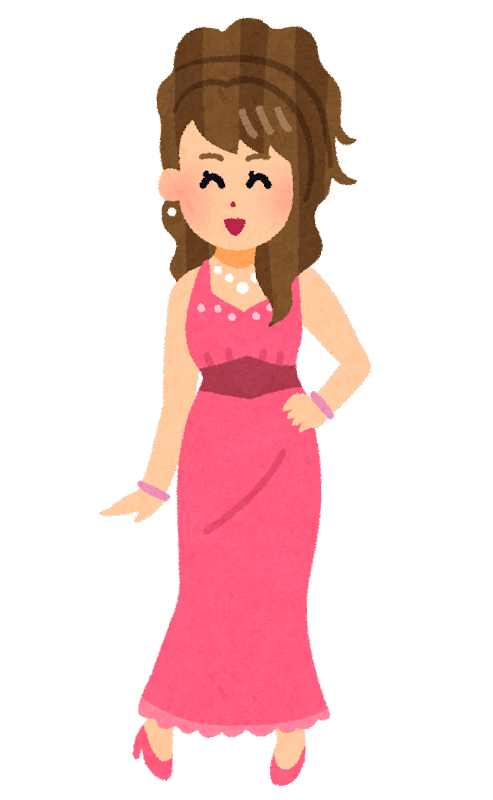
もう、あたしは仕事中よ
と言いながらもまんざらでもない様子で、よく見ると人差し指を一本立てている。男はそれでOKとばかりに頷いている。
これで商談成立。
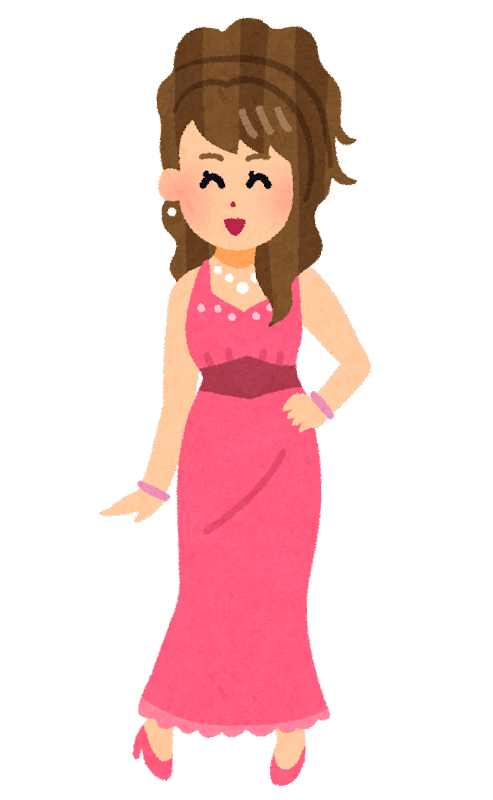
ネエさん、ちょっとお客さんと散歩してきま〜す♥
さっきの「お仕事中」はどこへやら、ネエさんと呼ばれた人にお金を渡し旅館へドボン。こういうシステムが成立していました。
これ、屋台を喫茶店に変えたら大阪の釜ヶ崎の青線と全く同じですな。
しかし、旅館へドボンといっても、元赤線の転業旅館には向かわないようでした。なぜなら元赤線は廃止後も警察にマークされており、ヘタにお泊まりすると警察に尋問され「痛い腹を探られる」から。
そのせいで転業旅館も大赤字、「アルバイト料亭」なんて上手いことやって継続してる大阪の元赤線に「視察」しましょうかしらん…という話で、梶山の筆は止まっていました。

「弁天地区」赤線の現在は今、どうなっているのか見てみましょう!
次ページへ続く!!



















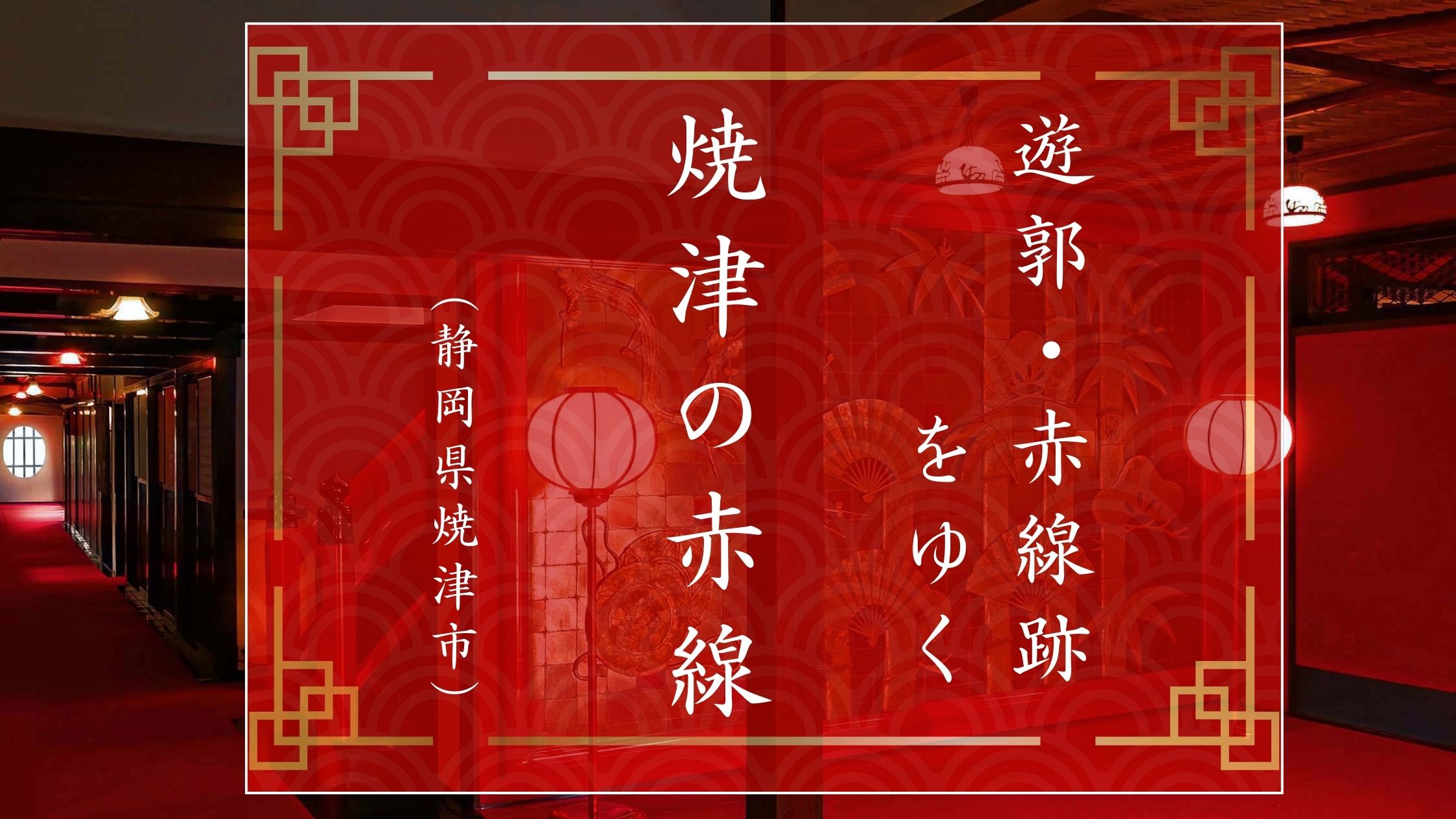
コメント