戦後の貝塚新地-そして赤線へ
空襲で焼けてしまった貝塚ですが、そこは遊郭、フェニックスのように蘇ります。焼けた遊郭がいつから営業再開したのかなどのデータは残っていませんが、おそらくすぐ再開したものと思われます。
一部『貝塚市勢要覧』には当時の「新地組合」の名簿が掲載されています。「カフェー」と記載されているので貝塚の業務形態はカフェーだったことがわかります。
そこに掲載されていた業者(屋号)は以下のとおり。
・梅の家
・竹家
・幸龍
・松家
・千歳
・深川
・花月
・上芳
・繰駒
・第二山村
また、『全国女性街ガイド』にはこう書かれています。
未亡人クラブが多く、大阪に住む女性が出稼ぎに行く。その数は百名を下るまい。(以下略
引用:『全国女性街ガイド』
この数が本当だとすると、赤線の接待婦数は遊郭時代のピーク時の3分の1くらいか。戦前の勢いそのままの紡績会社のサラリーマンが、鼻息を荒くしながら夜の貝塚の赤い灯のもとに消えていった情景が思い浮かびます。
が、ある資料に少し気になる記述が。
近年交通機関の発達と共に遊客の訪れは減少し、寂れつつあるときに売防法の施行となり速やかに解散した
引用:大阪府民生部の資料より
赤線を監視していた大阪府の関連部署の資料なので、ほのかに信憑性がありますが、道路の整備や電車のスピードアップなどで遊客の流れが変わったのかと思われます。
.jpg)
(貝塚市勢要覧 昭和二十九年版より )
貝塚カフェー街を空撮した珍しい写真です。右側が貝塚駅方面、左側が海です。真ん中を縦(東西)に貫く、少し幅が広い道路が遊郭・赤線の大通りで、赤い灯花盛りの頃は道の両脇に女性が並んでいたのだと容易に想像がつきます。
そして、これも貝塚にとっては運命の日である昭和33年(1958)4月1日、売春防止法適用1により店の赤い灯は消え、色街としての歴史は幕を閉じました。
その後は潜り売春が1件検挙されただけで、「旧業者はすべて土着の住民と言うべき永住者であったこと、経済力豊かな農家や他事業者、会社役員など法を犯してまで営業する必要がない」人たちだったこともあり、至って静かだったそうです。
幻の「貝塚ハイカラ街」計画
戦前は岸和田をしのぐ殷賑を極めた貝塚でしたが、売防法による赤線廃止はもちろん、工場移転などによる地場産業の衰退などにより貝塚駅前はさびれる一方だったと言います。赤線時代は、駅から赤線まで150メートルくらいの道を飲食店が軒を連ね、深夜まで賑やかだったと言いますが、それもなくなり「うらぶれた姿を晒している」と雑誌に書かれる始末。
指をくわえて衰退を見守るわけにはいかない地元は、昭和49年(1974)に貝塚復活計画を練り始めます。そこで目を付けたのが近木の旧遊郭。
当時は赤線廃止時の様相がほぼ手つかずで残っており、写真を見ると和風と洋風カフェー建築が入り乱れた、ちょっと不思議なワールドな感じでした。後述しますが、今も時間が止まったかのように、当時の建物がいくつか残っています。
が、昔はもっと残ってたのかと。たとえるならば、『千と千尋の神隠し』に出てくる「油屋」の前にある飲食店街のような雰囲気に近いと言えば近い。
今やノスタルジアとなってしまった大正の爛熟期の姿を再現し、再開発ビルの近代的な姿と対比させながらも、全体として一つのショッピング・センターとして機能させることを考案するに至ったのである。
引用:『貝塚近木旧遊郭蘇生計画』
要は遊郭の建物を利用し大正浪漫をテーマにしたショッピングモール、名付けて「貝塚ハイカラ街」。テーマは「灰色の南海沿線に『桜色の貝塚』が出現する」。伊勢の「おかげ横丁」のようなものを作ろうと言うイメージでしょうが、企画側は気合い十分、鼻息の荒さが文章からにじみ出ています。45年前の企画書なのに、読んでいるだけでものすごくワクワクしてきます。
しかし!
作られていないということは、いつか、どこかでポシャったんでしょうね(笑

さて、赤線がなくなった跡の貝塚の現在は?



















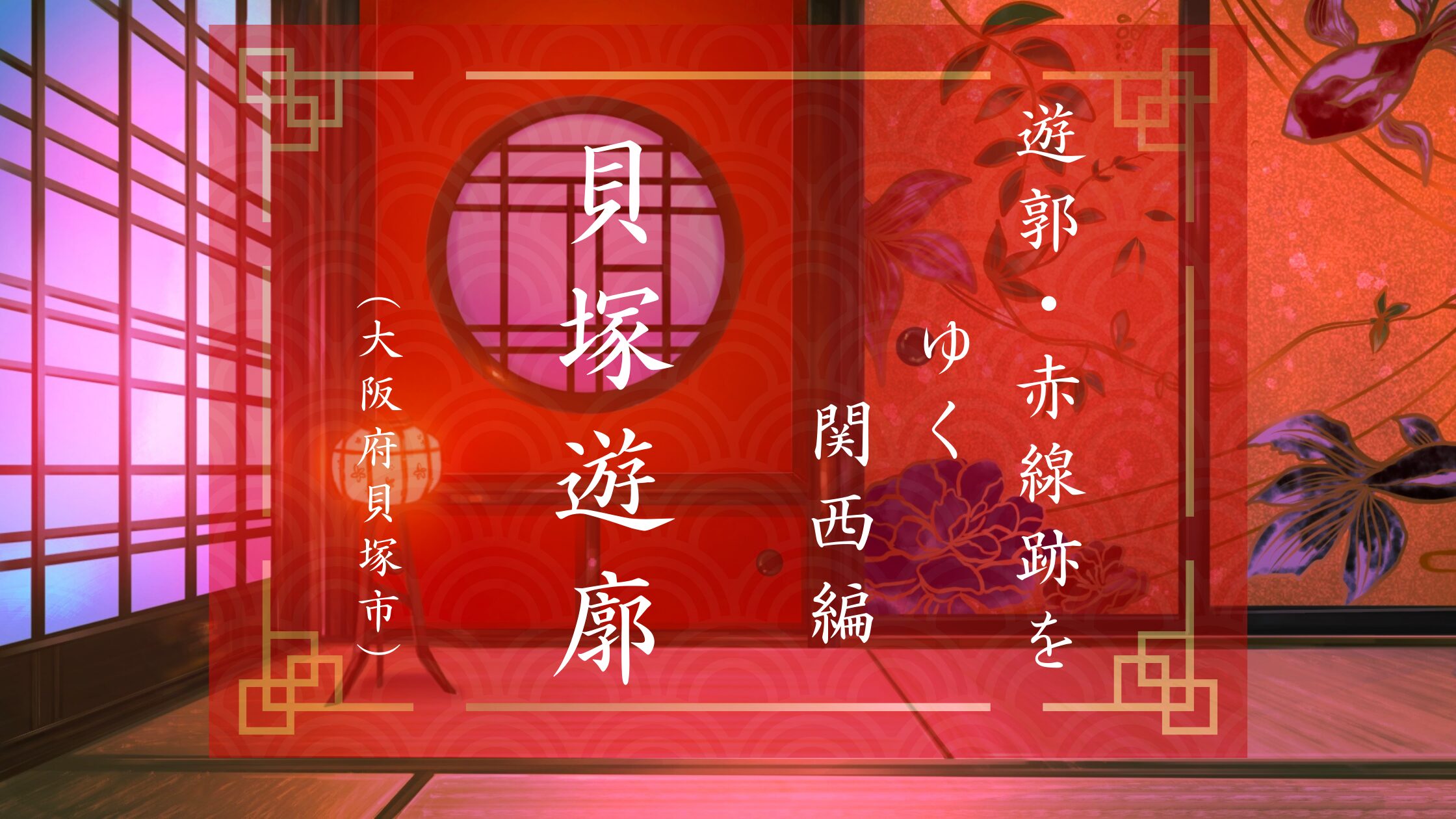
コメント
[…] 貝塚遊郭(大阪府貝塚市)|おいらんだ国酔夢譚 貝塚遊郭跡に行ってきました【大阪府貝塚市】 和泉国の色里・大阪 […]