貝塚が宿場町として繁盛するにつれ、旅籠は「泊り茶屋」を併設、「飯盛女」という女性を置いて客にサービスする許可を藩から得て営業していました。これが貝塚遊郭の原形。
史料によると、遊女は「飯盛女」でしたが「おじゃれ」「おしゃらく」とも呼ばれていました。
そんな江戸時代も後期のこと、遊郭にお千代という遊女がいたそうです。本名なのか遊郭での源氏名なのかは不明です。
そんな彼女が病気を患い故郷に帰る途中のこと。貝塚から紀州へと通じる道の途中で彼女は水を欲し、川辺へ寄ると自分の顔が流水に映りました。そこに見えた顔は、見るもおぞましい自分のやつれた姿でした。その自分じゃないような形相に彼女はショックを受け、
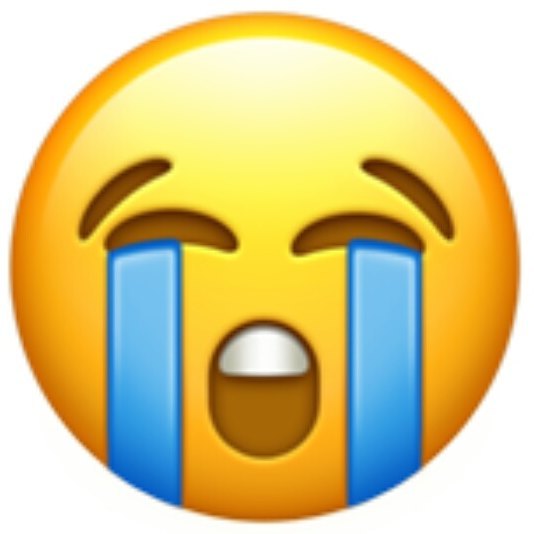
こんな姿では帰れない!
と自ら命を絶ったという悲しいお話が残っています。
一人の薄幸な女の悲しい結末ですが、それをかわいそうに思った地元の人たちが、ここに彼女の墓を建てて丁重に供養したそうな。

その墓が、貝塚市の山奥に残っています。「遊女の墓」とそのままのお墓は、確かに泉州から紀州へ通じる旧道に存在していました。
言い伝えによると、彼女が亡くなったのが文化10年11月14日、文化10年を西暦に直すと1813年。彼女が亡くなって200年以上経っています。
当時の情勢は、外国船が日本近海にあらわれ始め、ヨーロッパではナポレオンがロシアへ遠征し、寒さで全滅した時期。
また、当時の光格天皇がお千代の死の4年後に譲位、上皇となります。現在の上皇陛下のご譲位はこの時以来だと日本がざわついたのは記憶に新しい。
周囲に人が住んでいる気配はないのですが(ただし村の跡はある)、今でも地元の人が住んでいるのか、それとも訪れる人が置いたものか、花もちゃんと手向けられ、定期的に掃除もされているようです。
しかし、上の写真のものは比較的最近にできたものらしい。

その片隅に申し訳なさそうに鎮座している古い地蔵がオリジナル。
ここを訪ねたのは今年ではない7年前ですが、こうして名前が200年経っても知られ、墓が残っているだけでも、お千代さんはまだ幸せな方かもしれません。
名が知られていることが幸せかどうかは、あの世の彼女に聞いてみないとわかりません。が、名前さえ知られないまま、どこに葬られたかさえも知られないまま消えた一人の女性の人生が現在に伝えられています。
遊女の墓の場所
かなり山奥なので、地元民じゃなかったら車かバイクで行くことをおすすめします。
ただし、遊女の墓の前まへは車は入れないので、どこかで路駐必須です。
自転車なら、ロードバイクなどスポーツ系、電動アシスト自転車なら意外に余裕です。
水間鉄道は、日曜のみながら電車に自転車を搭載できるサイクルトレインサービスを行っているので、これを利用してサイクリングがてらの訪問も悪くはありません。





















コメント