東京の府中市、非東京民の中では東京の郊外市の中でも知名度が低めですが、鉄道が交わる交通の要衝であり、刑務所があり、そして競馬場がある。
個人的には、東京外大と多磨霊園があるところというイメージです。

府中は元々、甲州街道の宿場町として開かれました。
宿場町には飯盛女ありがつきもの安永6年(1777)、旅籠を営んでいた東屋甚蔵という人物が、代官所に飯盛女を置く許可を願い出た始まりです。
それを見た新宿の倉田屋太左衛門と、番場の鉄五郎の2名が続いて飯盛女を置いた旅籠(飯盛旅籠)を開き、3軒の「事実上の遊女屋」を開くことになりました。
が、鉄五郎はすぐに廃業したようで、18世紀末まで上記の2軒だけの状態が続きました。
久しく2軒しかなかったのはひとえにそれしか需要がなかったことだろうと思われますが、隣の調布五宿(国領宿、下布田宿、上布田宿、下石原宿、上石原宿)と八王子に遊女屋が栄えていたことも一因だったと推定しています。
一時は風紀上の問題で代官所から「廃業勧告」されたりしたものの、飯盛旅籠は幕末までなくなることなく、記録によると2軒増え4軒というところで明治時代を迎えます。
明治初期には「たつむろ」「いろは」「杉嶋(屋)」「松本(屋)」「田中(屋)」の5軒が記録され、明治14年(1881)には9軒にまで増加しました。
お馴染み『全国遊廓案内』には、こう書かれています。
甲州街道の宿場で、今だに古風な宿場気分の濃厚な処である。只肝心の女が土地の者ではなく、ズーズー弁の東北女である事が残念だ。
【全国遊廓案内】府中町宿場
貸座敷が5軒町の中に散在して、娼妓は25人居る。(中略)いろは楼、たつ村楼等がある。
『全国遊廓案内』はその名のとおり、各遊郭を淡々と紹介していくだけで、筆者(または編者)の所感、実際に行った感想はあまり書かれていません。が、この府中には所感が書かれています。
では、何と書かれているのでしょうか。
只如何にも田舎らしい気分がすると云ふ丈けで、態々やって来る程の処でもない。
『全国遊廓案内』
けっこうなボロカス具合です(笑
そのせいか、この府中遊郭はそれ以上発展の見込みもなく、命運はここまでのようでした。
戦争による遊興制限とともに妓楼の経営も打撃を受けていき、最後はお国のために近くの東芝などの軍需工場の従業員寮として明け渡しとなりました。
戦後には赤線として復活したという話もなく(隣の調布・八王子は復活)、戦争で府中遊郭は「死亡」したとみて間違いないでしょう。
府中遊廓は今ー性地巡礼
遊郭は時代の流れとともに郊外の「新開地」に集約化され、体よく端っこに追い出されるのが宿命でした。
が、『全国遊廓案内』の記述のように、府中は街道沿いに遊女や散在する、江戸時代の飯盛旅籠そのままの形態をを残していました。首都の遊郭にしては非常に珍しい。

資料から、府中に存在した妓楼の配置を番号であらわしてみました。
青線の甲州街道(今は「旧甲州街道」)を軸に、『貸座敷が町の中に散在』していることがわかります。
これが飯盛旅籠から出発した遊郭のオリジナルの姿で、近代に入り街中に遊女屋があるのは風紀上うんたらかんたらで郊外に集約され「廓化」し、遊郭となったという経緯です。

まずは①の「松本楼」は、戦後は家具屋になったそうで、現在はこの通り駐車場に。

その対面にあった「杉島(嶋)屋」はマンションになっています。
こちらは明治末頃に廃業したらしく、それ以降は病院になった模様。
ぶっちゃけ、「松本楼」跡の隣に「柏屋」がなかったら、どこがどこだか全くわからないところでした…。
ちなみに。

府中駅のすぐ隣に、「称名寺」という、踊り念仏で有名な時宗の寺院があります。

ここの墓地には、「杉嶋屋」と彫られた墓石があり、楼主だった林家の墓が残っています。

その片隅には、店で働いていたという遊女、飯盛女の墓が残されています。
墓石はおそらく遊女の名前か何かが刻まれていたと思われるのですが、長年の風雪で文字が禿げてしるものも多く、判別できません。


その中に一つ、地蔵の形が彫られた墓石があります。
右側には、「法岸童女・文久元年四月五日」と彫られており、左側には「俗名 きぬ」と。
「童女」は幼女のことなので遊女ではなく、おそらく遊女が産んだ子どもだったのでしょう。

『全国遊廓案内』に掲載されていた「いろは」の跡がこちら。
昭和まで残った妓楼の一つで、戦争中に接収され近くの東芝の工員向けの寮となりました。
妓楼のお仕事部屋はだいたい4畳一間なので、「工員の独身寮」としては実はビンゴな間取りでもあります。なので、戦争中は洲崎などのように遊郭もお国のためにと接収されたりしています。

「いろは」のほぼ対面には、「田鶴群」という名前の貸座敷が建っていました。
「田鶴」は「たづる」ではなく「たづ」と読み、慣習上「たつ」でも良いそうです。
「田鶴群」は、「たつむら」と不規則な読みをすることもあります。
つまり、明治時代の「たつむら」、『全国遊廓案内』に記載の「たつ村」は、ここの「田鶴群」で間違いないでしょう。

妓楼とは関係ないですが、府中宿沿いには100年、いや150年選手じゃないかという古い和風建築が、歯抜けのように残っています。
こちらなど、格子もはっきり残っていて昔の妓楼ってこんなんだったんだろうなと想像力の足しになりそうなものもあります。

甲州街道と鎌倉街道が交わる場所には沿いには、お上からの重要なお知らせなどが掲示された高札場が設けられていました。
そこから鎌倉街道沿いに2軒分南へ下った⑤の場所には、「田中屋」という妓楼がありました。
-1024x714.jpg)
田中屋万五郎という、府中で岡っ引きをしていた人物が作った妓楼とされ、『むかしの府中』にはここの図面が残っていますが、部屋数20とかなり大きな妓楼でした。
こちらは昭和15年(1940)頃に廃業し、昭和20年(1945)に村上という医師が買い取り戦後は病院として使われていました。
府中遊郭の元妓楼のうち、最後まで残っていた元妓楼でしたが、築120年と老朽化が進み、特に雨漏りが激しく、昭和48年(1973)に惜しくも解体。

現在は、建て替えられた「村上医院」がそのまま残っています。
ちなみに…

甲州街道沿いには大国魂を祀る大国魂神社があります。
府中宿の真ん中にドン!と君臨する存在感抜群の神社で、武蔵国の守り神、厄除けの神様として長年人々の信仰を集めてきました。
私の訪問時には秋の祭礼の真っ最中。参拝者も多く露店も並びまさに縁日の賑わいで、府中駅から神社への道は人・人・人。
朝早くに来ないとこんな人が少ない写真は撮れないという状態でした。
それはさておき、神社の中にある末社の巽神社には、この田中屋の名前が残っている神灯が残っています。
残念ながら本殿内は撮影禁止なので写真には撮らなかったのですが、19世紀の江戸末期に飯盛旅籠を経営していた「福本屋」という八九三との連盟で神灯を奉納したようです。
興味がある方は、訪れてみてはいかがでしょうか。
おわりに
東京の遊郭は、吉原や洲崎などの日本屈指のギガ遊郭や、「私娼窟界の吉原」こと玉の井などばかり注目が集まり、多摩地区まで視界を広げても八王子や調布の遊郭ばかり。ここ府中を取り上げている人は少ないように見受けられます。
だからこそ私が取り上げたわけですが、東京の穴場遊郭の歴史と現在、いかがだったでしょうか。
・『全国遊廓案内』
・『府中市史 下巻』
・『むかしの府中』
・『色街文化と遊女の歴史』



















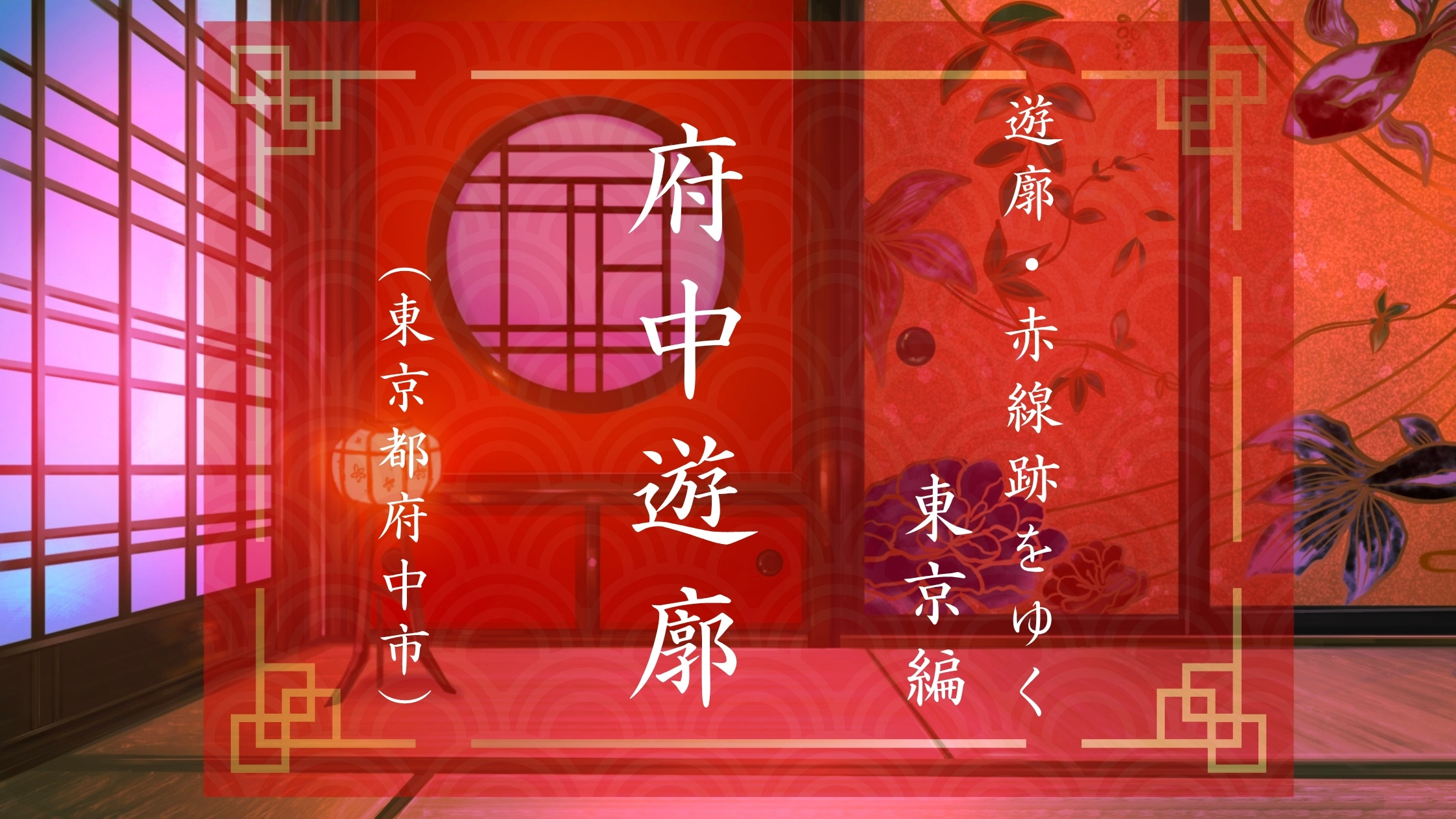



コメント