函館の「準遊郭」ー鉄砲小路と堀川新地
「函館大火」により焼け野原となった大森遊郭、その後の営業範囲は従来の半分となり規模も半減。娼妓の数も、大火前は300人超をキープしていたのが、大火直後の昭和10年(1935)のデータでは142人と半分以下に。そこから娼妓の数は減る一方でした。
遊廓の運営が廃娼運動や天敵カフェーの隆盛で厳しくなったところで、大火は泣きっ面に蜂だったようです。
遊廓は大火で整理されましたが、実はもう一つ整理されたものがあります。それは私娼窟。
函館では大火前から、街娼を含めた私娼が至るところで跋扈していました。1930年代初頭の函館の密売淫で検挙された人は、年間平均200人強。
これ、「運悪く捕まった人」だけなので、実数は少なく見積もってもこの1.5~2倍、あるいはそれ以上いたことは容易に推測できます。
同時期の札幌の密売淫検挙件数が数十件なので、おそらく札幌のすすきのをしのぐモグリ売春が、函館の街の至る所で行われていたのでしょう。
特に、造船ドックが並ぶ弁天の「鉄砲小路」は歓楽街としてかなり栄えており、現在の市電「函館どつく前」を降りたらカフェー(飲み屋)が何十軒も並ぶ歓楽街。函館漁港へ続く鰪澗町3は、私娼がウヨウヨしていたそうです。
遊郭は、公娼ゆえに廃娼運動家の目の敵となり、大正時代以降は人権という概念も広まって逆風に苛まれることとなりました。また、遊郭の方も老舗ゆえにだんだんと商売が形式主義となり、客も女も私娼窟や人カフェーに流れ、遊郭の経営を圧迫することとなりました。
しかし、私娼街も市内バラバラに点在していると当局側も困る。
それを災い転じて福となすと大火後に整理し、上述の「鉄砲小路」や新蔵前(宝町・東川町)にたむろしていた私娼を堀川町という場所に集約させることにしました。
準遊郭、「堀川新地」の爆誕です。

ここは小料理屋の営業形態をとり、いちおう酒は出たらしいですが料理は出ない。
それって「料理屋」なんかい!!とツッコミが入りそうですが、そんなの飾りです偉い人には(ry
店で抱える女の数は3〜6人ほどで、全体で100人強だったといいます。
「宝生館」という劇場を堀川町の中心部に作り、それを灯台のようにして客を集める営業戦略だったようだが、客層は不良や遊び人など、あまりガラが良くなかったと当時を知る資料に記されています。

堀川町のほぼ隣に陸軍の重砲兵聯隊が駐屯しており、日曜日には兵隊が駆け込んできたことは容易に想像できる…のですが、当時の書物によると兵隊が行くのは専ら遊郭で、堀川新地はスルーだったそうです。
おそらく、性病罹患を恐れた軍が堀川新地で遊ぶのを禁止したのでしょう。
堀川新地の大きな特徴は、日本人向けだけではなく朝鮮人経営の店もあったということ。
昭和17年(1942)の話ですが、函館健康保険組合の堀川新地の組合員のうち、日系13軒、朝鮮系が5軒となっていますが、朝鮮系と言っても札幌の白石遊郭の周りにあった私娼窟と同様、和服を着た朝鮮人なだったとのこと。
料金も、日系が泊まり5円〜に対し、朝鮮系は3円と安かったのが相場でした。

資料によると、堀川新地の場所はここあたりとなります。
また、堀川新地とは別個に「昭和新地」と呼ばれる遊里も爆誕していたようです。
場所は堀川新地の近く、「昭和橋近く、済生会病院の裏手」に20軒ほどあったようです。
「済生会病院」は現存しないのですが、上のGoogleマップの切り抜きだと「堀川町10」と書かれたあたりの場所のようです。
堀川新地は函館遊里史のターニングポイントを飾る重要なキーですが、函館遊郭を語っているブログには一切取り上げられていません。調査が浅いな。
しかし、昭和12年(1937)の盧溝橋事件から始まった大陸での泥沼の戦争は、遊興などけしからんという空気を生み出すこととなりました。それにより、ネオンやアルコールの提供が困難となり、昭和15年(1940)12月に遊郭などに休業命令が発せられ、一斉に休業を余儀なくされました。
戦後の赤線へ
そして戦後の赤線青線時代へと移りますが、函館の赤線青線は大きく分けて3つに分かれます。
一つは、旧遊郭である大森。公娼廃止後は料理組合として15軒、65人からスタート4。
二つ目は堀川新地。これは戦前からの流れ。
戦後の函館にはもう一つ、歓楽街が誕生します。
そこはピンク町と呼ばれ、函館駅前という立地条件の良さもあり繁盛していたといいます。
『全国女性街ガイド』にもその姿が記載されています。
目下は駅前ヤミ市の(中略)飲み屋が密集し、青森からの出稼ぎパンが赤線代用をつかさどっていて(以下略
『全国女性街ガイド』
ここは一杯飲み屋の形をした売春宿(青線)になっていて、お店の2階か奥に「本当のお仕事部屋」があるような形式だったのでしょう。
戦後最盛期と思われる昭和28年(1953)の保健組合員の数は、
・大森:19軒
・弁天・堀川新地:14軒
・ピンク町:142軒
と、ピンク町が完全に既存を食っている感があります。
なお、この数字イコール業者数ではないのでご注意を。


「駅前遊郭」ということで栄えたピンク町ですが、それが逆に仇となり再開発の真っ先の犠牲に。
あたりはさっぱり整地されましたが、数年前でも

ああこれそうやったんやろな…
と思えるものが数軒残っていました。
また、『全国女性街ガイド』によるともう1ヶ所、青線的売春窟があったようです。
それよりぐっと落ちた曖昧屋が弁天町に43軒139名…
『全国女性街ガイド』
弁天町とは、前述した函館どつくの場所の私娼窟のこと。堀川新地に集約されても、やはり船員の需要が高かったようですね。
昭和20年代の航空写真を見てみると、弁天町周辺には函館どつくはもちろん、他に工場や倉庫が海沿いに並び、おそらくここで働く労働者や漁師が主な客だったのではないかと思われます。

戦前のカフェー町からの歓楽街は、筆者の調査不足につき場所は判明していません。
が、資料からの証言を断片的に拾ってみた結果、路面電車の終点「弁天」(現函館どつく)から函館漁港へ続く道にあったと推定しています。
そこは昔の華やかさが嘘のように、静かな住宅街になっています。
停留所近辺も含め、今の姿を見るとここ界隈がかつて女の嬌声に賑わった場所だなんて、到底信じられない気分です。

北海道の遊郭については、こちらもどうぞ!
・函館市史(デジタル版)通説編3
・全国遊廓案内
・最近實測函館精圖(1927)
・『道南の女たち』道南女性史研究会∥編著 幻洋社(1995)
・『北海道遊里考』
・『北海道統計書』
・『函館の履歴書』元木省吾著 1972年
・『函館日々新聞』 昭和9年9月8日〜12月18日「おらが町内を語る」











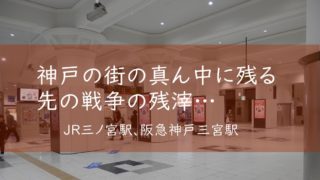







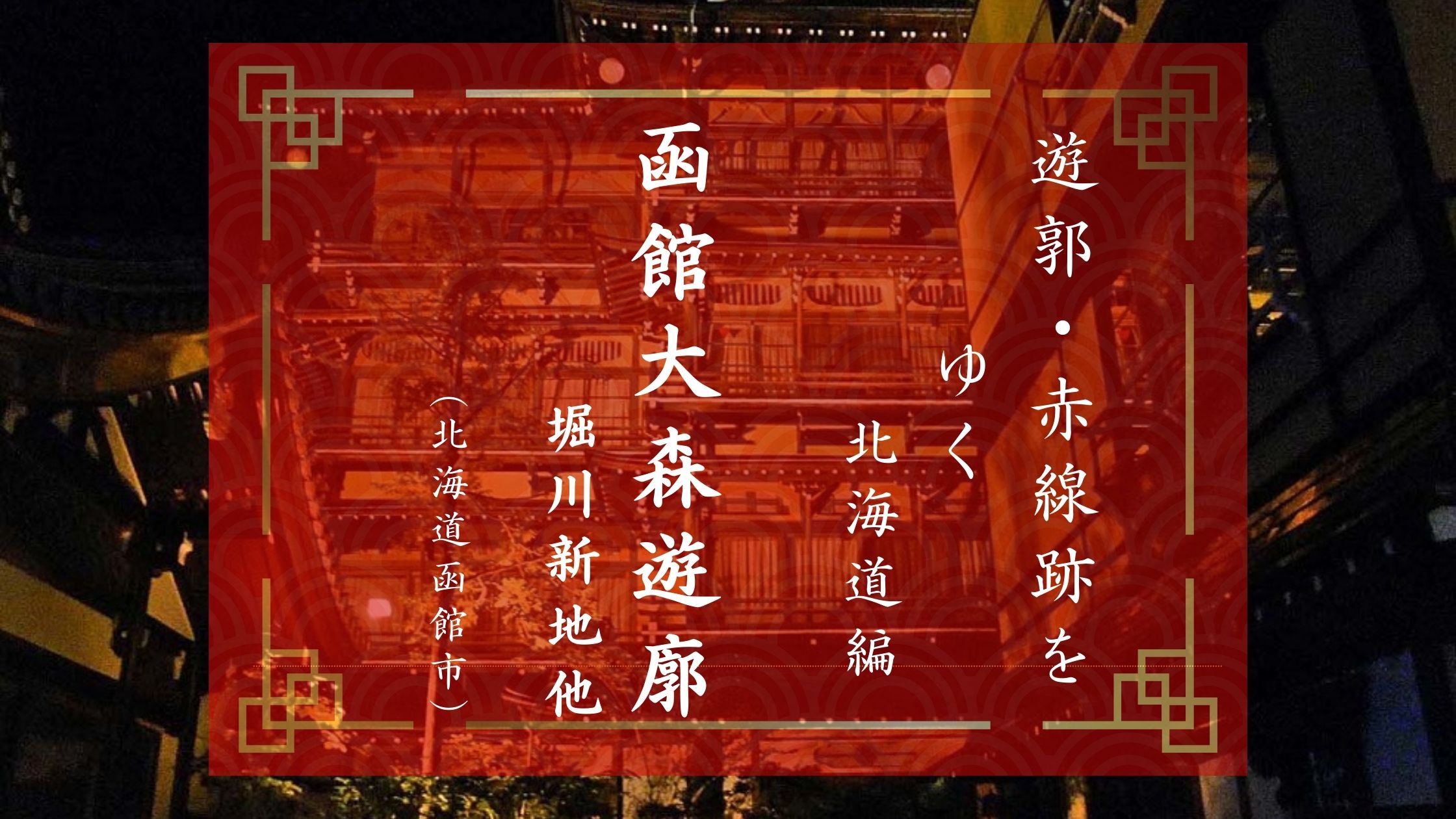


コメント