妓楼はトイレも豪華だった!

1階の奥に鎮座するは、トイレです。そのまま便所なのですが、同じものが3つある。これって意味あるの?と。意味があるから分けているという前提での私の勝手な想像ですが、やはり他の遊客と顔を合わせないよう、個室形式にしたからではないかと。
昔はほぼ公然と女遊びができたとは言え、顔見知りと鉢合わせるとやはりバツが悪い。会社の同僚とラブホのエレベーターでばったり…なんてイヤでしょ?それと同じことです。
そして、トイレ前の床を見てみましょう!

(画像:『知の冒険』様より)
ただの床でした(笑
しかしここ、かつては3分の2がガラス床だったそうで、その下には水槽があり金魚が泳いでいたとか。修繕が始まった時はガラス床にヒビが入り、危ないと写真の床に替えられたそうな。
思い出せば、最初の訪問時ここあたりは立入禁止、用は他の所でやれだったのですが、ガラス床との関係があったかもしれません。

そのガラス床の一部が、裏庭に展示ならぬ放置プレイされています。人間の重みに耐えられるほどの厚みたるやすごいもの。ガラスの床に金魚だけでもびっくり仰天ですが、このガラスだけでもけっこうええ値段しまっせ。
そこで、一緒に回っていた方がつぶやきました。

淀屋の逆張りやな…
あーなるほど!と私も納得したのですが、これはどういうことか。
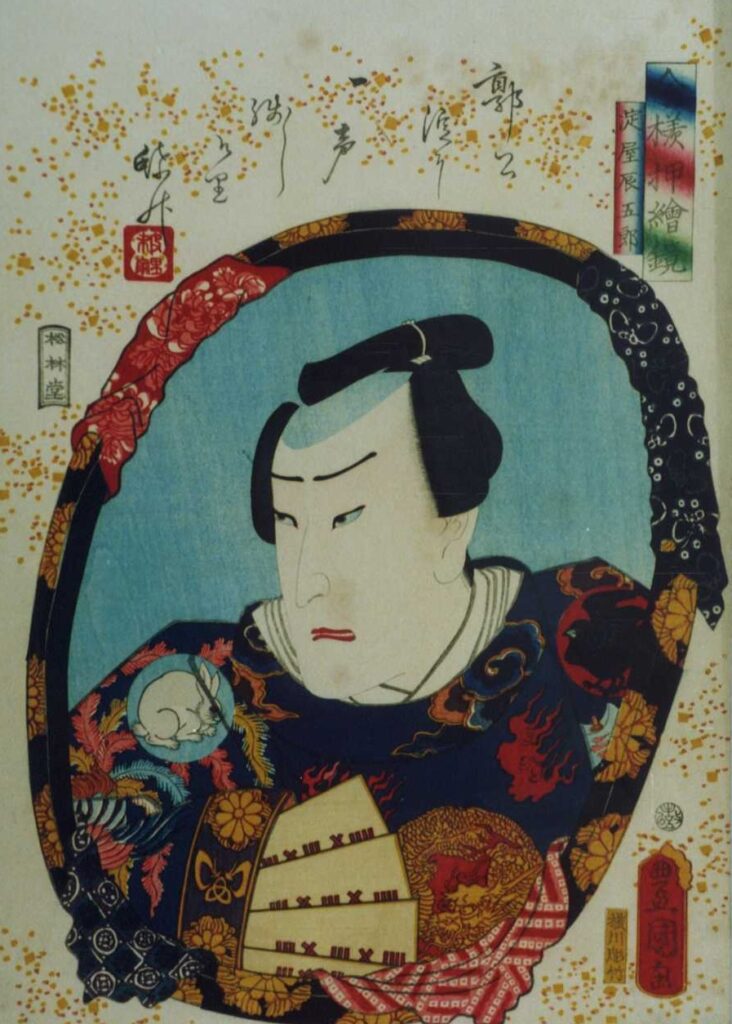
「淀屋」とは、江戸時代初期の大坂にいた豪商、淀屋辰五郎のこと。
淀屋は商売で大もうけし、大阪を「天下の台所」たらしめた一人でした。
その贅沢の一つに、「天井金魚」なるものがあります。

淀屋は「夏座敷」と称して大広間の天井をガラス張りに替え、その上に水を入れ金魚を泳がせたというのです。有名な話ですが元ネタは『元正間記』という書物、それくらいの贅沢ができたほど淀屋は財をたくわえたというのです。
が、贅沢三昧が幕府の逆鱗に触れ1、全財産をボッシュートされてしまいました。赤穂浪士による討ち入りの数年後のことでした。
淀屋はお取り潰しになってしまいましたが、屋号は実は番頭だった牧田仁右衛門が淀屋から暖簾分けしてもらい、故郷の倉吉に帰った後に淀屋を復活させます。
牧田家は代々淀屋清兵衛を名乗り、倉吉随一の商家として倉吉の発展を支えました。

また、大阪でも「淀屋橋」という駅名にそれが残っています。
3階にもあるトイレ

旧川本楼には、3階にもトイレがあります。
階段を上ると目の前に現れるのは、トイレです。右から書かれた「所便」がレトロ感を醸し出していますが、当時そのままのものなのである意味当たり前。
しかし、ここである謎が浮かび上がります。
水洗便所がふつうになり、高層階にもトイレがあるのが当たり前になった現代ですが、川本楼が建てられた当時はくみ取り式が当たり前。便所は1階に設置されていました。
しかし、ここには2階どころか3階にトイレがあるのです。どうやって用便を下に落としていたの?と。
市が買い取った時、ここはすでに便所の用を終え便器も撤去されていたようで、男子用トイレだったようだけれども、詳しいことはわからないとのことです。
しかし、男子用ならば管で1階まで落としてたのではないかと容易に想像できますが、そんなに簡単にはいかないのだろうか。そこらへんはわかりません。
わかっているのは、3階のここに「所便」があったということ。今後の研究が待たれます。























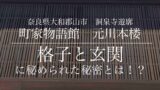



コメント