濹東綺譚に描かれた、南の解放運動の結果
南は己の甘っちょろい考えを嗤ったものの、それは本当に無駄だったのか?
その結果は、予想もしなかった形となってあらわれます。
玉の井を描いた小説・文学作品として真っ先に思い浮かべるものとして、永井荷風の『濹東綺譚』(以下『墨東』)があります。しかし、もう一つ、下村千秋の『天国の記録』(以下『天国』)という作品もあります。『墨東』が有名になりすぎて『天国』の知名度はかなり低いですが(読了後は鬱になるくらいストーリーが重いのもあると思いますが…)、『墨東』と合わせて「玉の井二大小説」と私は勝手に言っています。
『天国』と『墨東』は、舞台こそ同じ玉の井なものの、出版は前者は昭和5年(1930)1、後者は同12年(1937)。
前者は酌婦が使い捨てのモノ扱いを受け、使い物にならなくなったらゴミのように捨てられ、最後は主人公が発狂して死んでしまう悲劇に対し、後者は純水のような男と女のラブロマンス。同じ場所なのかというほど、環境が違いすぎます。
もちろん、『墨東』は永井荷風がその文才でヘドロをろ過し、純水にまできれいにまとめ上げている感は否めないものの、明らかに『墨東』の酌婦は明るく、そして一人の人間として人間らしく生きています。
本記事を丁寧に読んでいると、ここでピンと来ると思います。
『天国』は南が玉の井の酌婦の現実を知り私娼解放運動を起こす前、『墨東』は「玉の井女性向上会」が待遇改善を要求しそれを得た後のことなのです。
その証拠が、『墨東』には描かれています。
お雪は窓から立ち、茶の間へ来て煙草へ火をつけながら、思出したように、
『墨東綺譚』岩波文庫P129-130
「あなた、あした早く来てくれない」といった。
「早くって、夕方か」
「もっと早くさ。あしたは火曜日だから診察日なんだよ。十一時にしまうから、一緒に浅草に行かない。四時頃までに帰ってくればいいんだから」
(中略)
「何か買うものでもあるのか」
「時計も買いたいし、もうすぐ袷だから」
主人公の「わたし」とヒロインお雪との何気ない会話ですが、お雪が「浅草に買い物に行く」「時計を買う」と言っているのは、「玉の井女性向上会」がGETした権利「外出の自由」「買い物の自由」が機能していることの証左。
『天国』の酌婦が絶対不可だったことを、『墨東』の酌婦はいかにも当たり前のように行っているのです。
荷風が『墨東』を書くために玉の井通いをしたのは、昭和11年(1936)のこと。南喜一の人生と照らし合わせると、南が玉の井私娼解放運動から身を引き、「女が私娼窟に入らなくて良い社会を作る」方へ舵を切った翌年にあたりますが、その時にはすでに玉の井の酌婦たちの待遇は良くなっており、それを荷風がありのままに描いていたのです。
「自分の運動は全くの無駄だった」
という南の嘆息は全くの杞憂。春秋の筆法でいけば、南の運動が成功していなければ現代に名を残す荷風の最高傑作が生まれることはなかったのです。また、荷風もここまで有名ではなく、ただの偏屈な変人おじさんで終わってたかもしれません(笑



















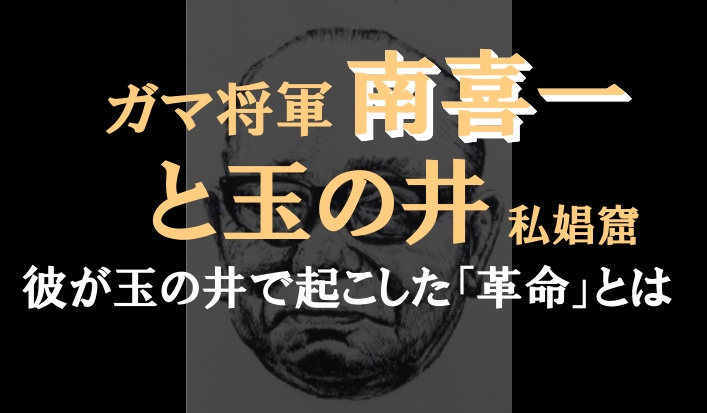
コメント