中書島遊郭略史
京伏見の一角をなす中書島。
「島」とついているように、地図をよく見ると宇治川と水路に囲まれた島です。
江戸時代、ここは京から大坂への水運の中継地として大いに栄えました。宿場町も形成され、ヒト・モノ・カネの集積地へ。
となると遊里ができるのは必然。ここには公許の色街が置かれ、井原西鶴の『好色一代男』や十返舎一九の『東海道中膝栗毛』にも登場し、戦後昭和の売春防止法施工まで「性地」として栄えました。

中書島の遊郭は、おけいはんこと京阪電鉄中書島駅から数百メートル北上した「東柳町」「西柳町」にありました。
昭和初期の『全国遊廓案内』によると、中書島遊郭の貸座敷数は84軒、娼妓(遊女)の数は約400人。規模は全国でも中の上といったところでしょう。
戦後も、公娼としての遊廓が廃止された後も貸席と業態を変え、昭和31年(1956)末時点で業者58軒、接客婦(という名の売笑婦)は183人と、そこそこ栄えていました。
しかしながら、
中書島
『全国女性街ガイド』昭和30年
ここも京都郊外。六十九軒に二百二十八名の関西女性がいる。
旧十六師団があった頃は盛んだったが、今は安売り七百円で客を呼んでいる。
この700円が泊まりなのかはわかりませんが、泊まりであれば京都市内の相場が1000〜1200円を考えると確かに「安売り」です。
昔は第16師団という上得意様がいたけれども、その上客が敗戦でごっそりいなくなり、「安売り」をアピールしないと客が来ないほどに寂れた…と推測できます。
そして、遊里史にとっては「その時歴史がひっくり返った」昭和33年(1958)3月にて、江戸時代から続いた紅い灯は一斉に消えることとなりました。
中書島遊郭に関しては、西口克己の小説『廓』に詳しいです。
小説ですが遊郭の描写がリアルで、「事実を元にした小説」に等しいその内容は、この類の歴史に興味がある人は必読です。
中書島遊郭にあったカフェー建築
そんな中書島にはかつて、一度見ると誰もが忘れられないような奇抜な赤線時代の建物がありました。


この色使い、けばいを超えて美すら感じます。
窓の上のステンドグラスなどは現物を見ると非常にきれいだったのですが、撮影者の腕がヘタクソなせいで全然映えません(泣
『赤線跡を歩く』にこの建物が紹介されていますが、私もそれを見て見に行った者の1人。画像のデータによると20年前のことで、私の性地巡礼者としての3軒目の探訪でした。ちな、最初は大阪の貝塚、2軒目が堺の龍神・栄橋。つまり地元ね。
しかしながら、写真として残っているのはこの2枚のみ。
まだ駆け出しの頃だったとは言え、撮影センスのなさに当時の自分を殴って差し上げたい気分です(笑)
20年前の心境はもう忘れましたが、本に掲載されていたその姿を見ただけで、「おなかいっぱい」になってしまったのでしょう。
若い頃は、

写真なんか撮らなくていい、自分のメモリー(記憶)に残しておけばそれでいいのさ
なんて格好つけて写真なんて撮らず、後年にしまったと後悔することなど、星の数ほど存在します。
今は記憶力減退と、その若い頃の「ええかっこしい」に対する後悔から、真逆の撮影魔になってしまいましたが(笑)
なお、この建物は私が撮影した数年後に解体されたと聞いています。撮影センス0だったとは言え、2枚だけだったとは言え、残しておいてよかった。



















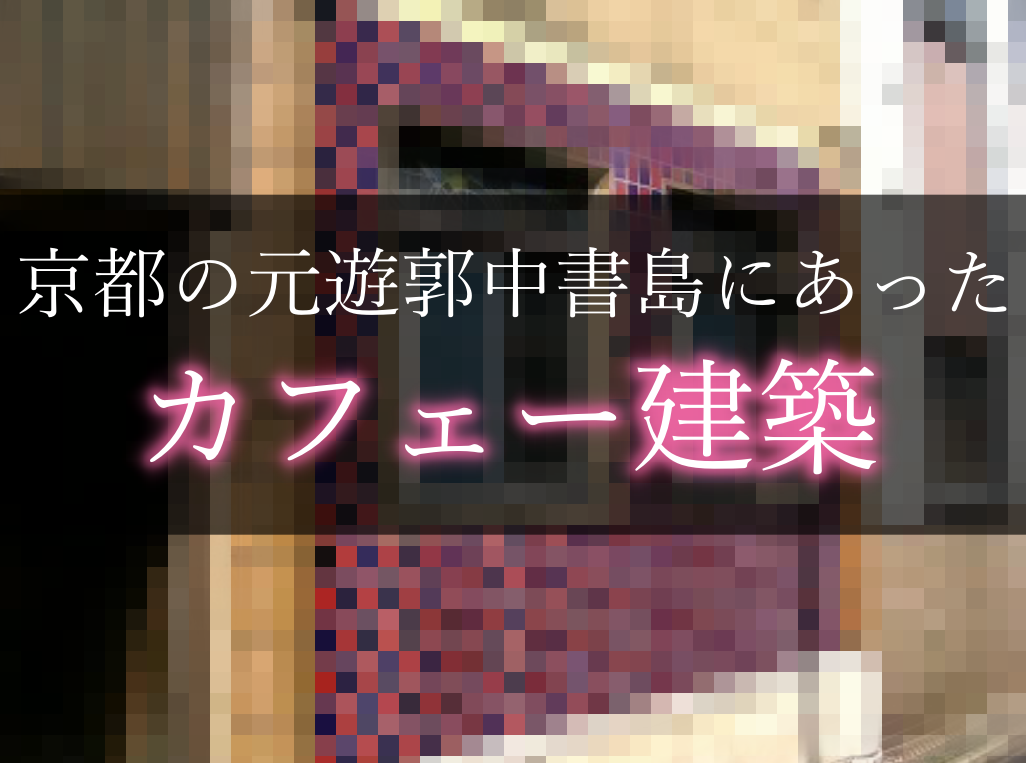
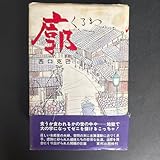

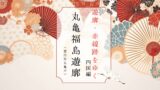
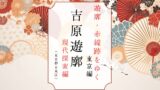
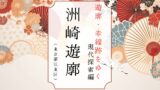
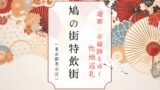
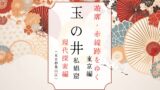
コメント