函館大火と大森遊郭
大森遊郭の衰退のとどめの一撃となったのは…またまた火事。1934年(昭和9)、大森遊郭にとって運命の「その時」がやってきます。
まだ残雪と寒さが抜けない3月21日午後、台風もどきの爆弾低気圧が北海道南部を襲い、函館では瞬間風速2~30mという強風が吹き荒れました。この日の風速は、記録に残る函館市1日平均風速ランキングの第3位となっています1。
この強風で住吉町の木造住宅が倒壊、そこから周囲に燃え移った火は折からの強風に煽られ、函館市内を焼き尽くしました。
また、風による電線の断線で全市が停電となり、火災報知器などが機能しなかったことも被害に拍車をかけたといいます。
前回二つの遊郭移転の原因もそうだったように、函館は幕末~昭和にかけての「大火」と呼ばれる大火事の回数が、市史の記録だけでも30回。
はた目から見ても何回燃えてんねんというくらいの被害を被っているのですが、この火事は規模や被害が他に比べて類がなく、俗に「函館大火」と言えば昭和9年のこれを指します。
また、この大火以降函館の人口が減少したのに対し、札幌がその間に人口を抜き北海道一の街となります2。この大火は、北海道一の街が名実ともに函館から札幌へ移ったきっかけでもありました。

函館市のデータによると、大森遊郭には午後9時頃に火が移り、あっという間に遊郭及びその周辺を焼き尽くしました。被災地図を見ても遊郭は真っ赤に塗られています。

北海道一の規模を誇った大森遊郭の栄華は、このようにすべて灰と化しました。遊廓の端にある大森稲荷の鳥居が丸見え、周囲に建物らしいものは残っておらず遊郭の大門だけ残っているのがかえって不気味に見えてしまいます。

明治40年の大火で現在地に移り、遊郭からも信仰を集めた大森稲荷神社には、大火で真っ黒になった狛犬が現在もそのままの姿で残っています。
ところで、火事での死因はほとんどが焼死または一酸化炭素中毒です。確かに、火事で死んだと言えばこの二つを考えるのが常識です。ところが、この函館大火の変わったところは、水死・凍死者(1,134人)が全死者数(2,198人)の半分以上。
もちろん焼死者もいますが、火事なのに死因の第一位ではないというところ。それはなぜか。

火事のあまりの勢いに、住民は南部の海岸(大森浜)に逃げ込みました。しかし火はそこまで迫り、避難した人の衣類に火がつき海岸も地獄絵図となりました。
熱さに耐えかねて、人々は海に逃げ込みます。が、海は海で低気圧により大荒れ。海に逃げた人も大波に呑まれて溺死してしまいます。
辛くも波から逃れた人たちも、当日の最低気温は-2℃、翌日は-10℃まで下がるという不運も重なり3、雪も降る中の強風と低温により凍死。
風、火、高波、低温の四要素が死神となり暴れまわった中、人々はさぞかしパニックだったことでしょう。
遊廓の女性たちも、当然ながら逃げたのですが、近くにあった大森の海岸に逃げた遊女は軒並み亡くなったそうです。

大火後の遊郭はどうなるのか?
そしてこれがきっかけで誕生した「新新地」とは?
堀川新地の誕生
運営が上記の理由で厳しくなったところで、この大火は泣きっ面に蜂だったようです。
遊廓は大火で整理されましたが、実はもう一つ整理されたものがあります。それは私娼窟。
函館では大火前から、街娼を含めた私娼が至るところで跋扈し、遊郭どころか函館の風紀も乱していました。
しかし、私娼街も市内バラバラに点在していると当局側も困る。
それを災い転じて福となすと大火後に整理し、「弁天」の「鉄砲小路」や新蔵前(宝町・東川町)にたむろしていた私娼を堀川町という場所に集約させることにしました。
準遊郭、「堀川新地」の爆誕です。
堀川新地については、こちらのブログをどうぞ。
戦後の赤線へ
そして戦後の赤線青線時代へと移ります。
函館に限ったことではないですが、終戦後からの混乱期はみんな食うことで精一杯な社会の中、戦争で家族を失った女性たちがメシの食いつなぎのために身体を売ることが珍しくありませんでした。
GHQは昭和21年(1946)1月21日に「日本における公娼の廃止に関する覚書」を発表し、日本の公娼制度はこれにて終焉を迎えます。
当然、大森の遊郭は解散…するかと思いきや、そのまま残りました。もちろん、「料理屋」などに看板を変えて。つまり、「公娼」が廃止になったから「私娼」、つまり赤線として継続となったのです。
理由は、街娼などのヤミ売春の増加。
これも函館に限ったことではなく、警察は「やむを得ない措置」としてあるエリア限定で売春を「黙認」することにしたのです。
「赤線」「青線」の誕生です。
赤線・青線の外で営業する街娼は違法として取り締まることになったのですが、それもだんだんと曖昧になってきて、東京では

町全体が赤線じゃねーかww
と苦笑するほどの有様になってしまったのです。
函館の赤線青線は大きく分けて3つに分かれます。
一つは、旧遊郭である大森。公娼廃止後は料理組合として15軒、65人からスタート3。
二つ目は堀川新地と鉄砲小路。これは戦前からの流れ。
戦後の函館にはもう一つ、駅前に歓楽街が誕生します。
そこはピンク町と呼ばれ、函館駅前という立地条件の良さもあり繁盛していたといいます。
『全国女性街ガイド』にもその姿が記載されています。
目下は駅前ヤミ市の(中略)飲み屋が密集し、青森からの出稼ぎパンが赤線代用をつかさどっていて(以下略
『全国女性街ガイド』
ここは一杯飲み屋の形をした売春宿(青線)になっていて、お店の2階か奥に「本当のお仕事部屋」があるような形式だったのでしょう。
戦後最盛期と思われる昭和28年(1953)の保健組合員の数は、
・大森:19軒
・弁天・堀川新地:14軒
・ピンク町:142軒
と、ピンク町が完全に既存を食っている感があります。
なおこの数字は、イコール業者数ではないのでご注意を。


「駅前遊郭」ということで栄えたピンク町ですが、それが逆に仇となり再開発の真っ先の犠牲に。
あたりはさっぱり整地されましたが、数年前でも

ああこれそうやったんやろな…
と思えるものが数軒残っていました。
そして運命の日、昭和33年(1958)の3月に、大森遊郭は明治以来の歴史に幕を閉じました。
が、街娼は売防法施行後も街角に立ち客を取っていたそうで、ピンク町も青函トンネルが開通し時代が昭和から平成になるまで、ヤミで行われていたという話を聞いています。

北海道の遊郭については、こちらもどうぞ!
・函館市史(デジタル版)通説編3
・全国遊廓案内
・最近實測函館精圖(1927)
・『道南の女たち』道南女性史研究会∥編著 幻洋社(1995)
・『北海道遊里考』
・『北海道統計書』
・『函館の履歴書』元木省吾著 1972年
・『函館日々新聞』 昭和9年9月8日〜12月18日「おらが町内を語る」



















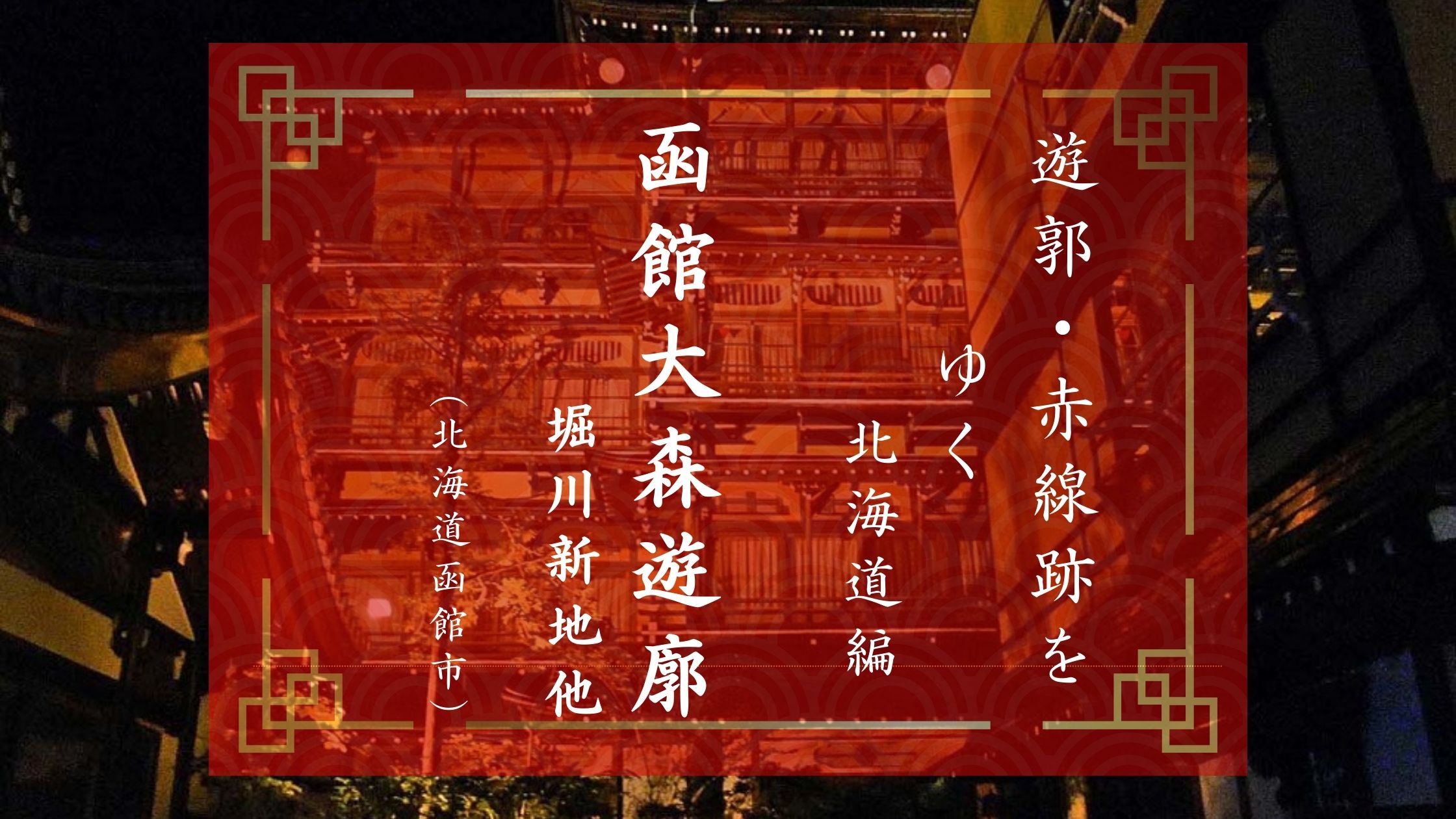
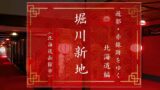


コメント